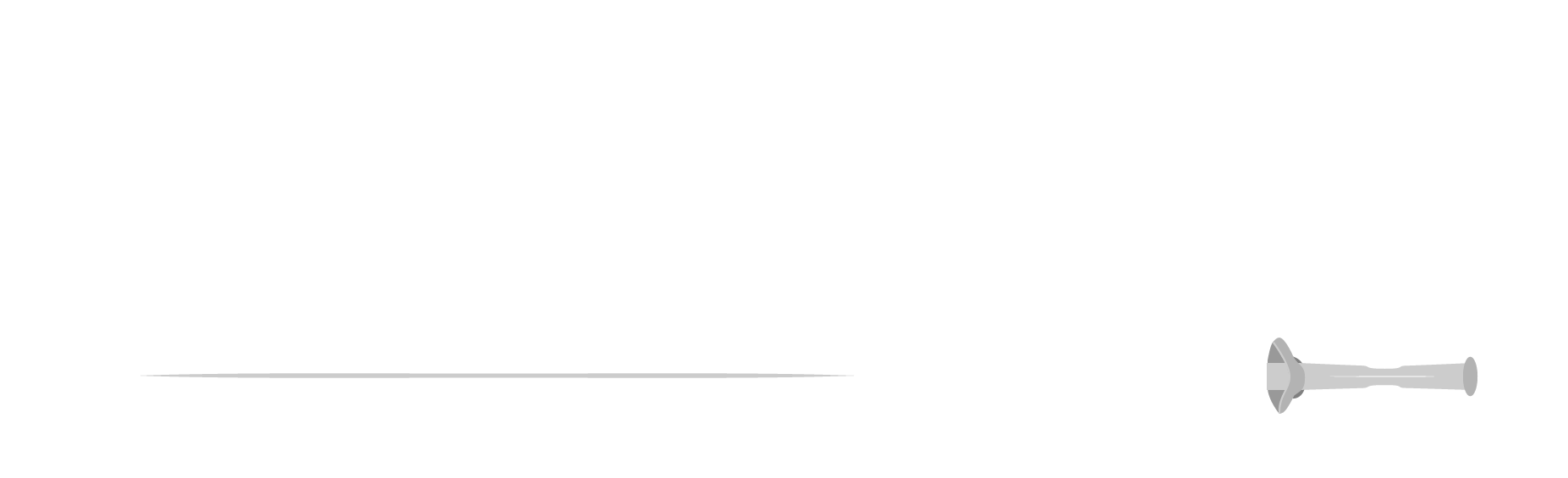和幸庵は、歴史が香る神社仏閣に囲まれた「衣笠」の地にあります。
世界遺産・重要文化財の金閣寺、梅花祭の天満宮、桜の名所平野神社、遅咲きの桜と仁王さんの御室仁和寺、五山の送り火では衣笠山に大の字の光が灯ります。また、瀧安寺の石庭、雲龍図の天井画で有名な妙心寺など、いずれの場所にも歩いて訪れることが出来ます。すぐ隣の「ご陵さん」と呼ばれる二条天皇御陵からは鶯の囀りが聞こえます。
このような立地の「衣笠」をこよなく愛した日本画家の木島桜谷が昭和八年に居を構えたことにより、彼を慕う芸術家達が集まる「衣笠芸術村」としてこのあたりは賑わっていきました。
当時、京都は角倉了以が水運を拓いたことにより材木業が盛んでした。ある材木商が、芸術村にふさわしい建物と庭を造りました。天井には網代、格子、船底など、多彩な細工が用いられ、廊下や玄関のすみずみに至るまで材木の使い方や見せ方に枠が凝らされています。お茶室の前の廊下には“なぐり”が施されるなど、材木商ならではの心意気が感じられます。部屋ごとの書院や床には、デザインや工夫がなされ襖にも四季の花々が順に描かれています。庭の石や燈籠も相応しいものがバランス良く配置されています。
福徳相互銀行の創設者の一人であった祖父の黒田巌が気に入り譲り受けたと聞いています。それが「和幸庵」の始まりです。元銀行本店建て替えのとき、玄関にあった灯籠は、本店の象徴として和幸庵の玄関前に移されました。「右金かく寺」と書かれた石の道標は、明治頃に既にこの地にあったようです。
庭の中央には樹齢二百六十年以上と言われる赤松が据えられ、その姿は龍が玉を持って空に登るように見えることから、幸運を呼ぶ松「福龍松」と名付けられました。母の代では樹の気を貰いに訪れる方も多かったようです。昔は井戸や中央の池には清水をたたえていました。庭全体は杉苔で覆われていて、京都らしい風情を醸し出しています。玄関と門の壁は錆び壁、塀は墨入り壁になっており、歳月を経ることに趣を増しています。中央の庭石「陰陽石」は、この世界のエネルギーの動きと成り立ちを象徴しています。陰陽めにあたるところにふれてを両手で触れて祈ると自分の中の陰陽、天地の陰陽が整うと聞いています。
平成二十八年、京都市の文化芸術部市推進事業の「京都を彩る建物や庭」に認定、選定されました。
私と弟の代になり、祖父母、父母の思いをついで、昭和レトロな雰囲気を楽しんでいただきながら、「和」の心を紡ぎ「幸」せあふれる本当の自分との出会いを体感していただく「庵」として後世に繋ぎたいと願っています。
一人ひとりが本当の自分に出会い、思いどう思いどおりの人生を生きていくことにより、その集合意識である世界は自然に平和となるでしょう。 世界まほろば、宇宙まほろばを実現し拡げていく拠点として、訪れてくださる方々に、日本人の根底に流ている慈しみわするこころをお届けします。
※なぐり: 木材の表面を手斧ちようなで削って凹凸をつけて仕上げること。またその面